登山を始めようとしている方が一番初めに感じる壁は、「装備は何をそろえればいいのかわからない」ということだと思います。
早速ですが、結論です。
「1,000M前後の山がメイン。たまに、2,000M前後の山に行くこともある」という人を想定しています。
ここまでの装備で、費用は安く買えれば3万円、ちょいと高めで5万円程度となります。
なお、1泊以上することを考えている人に必要な装備は、さらに2つあります。
この記事では、大学生のころ登山部だったひよこSE(@PiyoOct)が、夏山登山に必要な装備と費用について、解説します。
必要な装備その1:登山靴
登山靴は、必ず購入してください。
普通のスニーカーだと、登山道では滑って危険です。
登山靴選びのポイント
登山靴選びのポイントは、防水性・足首の高さ・フィット感の3つです。
※靴は、フィット感が重要なので必ず登山用品店で試し履きして購入してください。
登山靴の足首の高さには
- ハイカット
- ミドルカット
- ローカット
の3種類がありますが、一番けが(特にねんざ)をしにくいのは、足首をしっかり固定するハイカット。
▼ハイカットってこんな靴

ただ、ハイカットは靴が重いし、値段が高いので。
本格的な登山であるか?を基準に、下記の通り登山靴を選ぶといいです。
- 北アルプス・南アルプスの高山を登る方はハイカット
- 1,000~2,000Mの山を登る方はミドルカット
登山靴の費用
登山靴の費用は、
- ハイカットで15,000円~20,000円
- ミドルカットで10,000円~15,000円
が目安です。
おすすめのお店は、お近にある登山用品店です(汗)。
値段的には、モンベル、THE NORTH FACE、コロンビアが安めかと。
モンベル
- 近くのお店:モンベルの店舗情報
THE NORTH FACE
- 近くのお店を探す:THE NORTH FACEの店舗情報
コロンビア
- 近くのお店を探す:コロンビアの店舗情報
必要な装備その2:ザック
次に必要となる装備は、ザックです。
「普通のリュックサックでも・・・」と思うかもしれませんが。
体への負担が全く違うので、登山用ザックで行くべきです。
ザックの選び方
登山用ザックの選び方は、容量です。
- 日帰り登山であれば、20L~30Lの容量
- 1泊以上は、30L~60Lの容量
▼大学生ならこんな感じのガチのやつ買わされる(汗)

「登山用のザックを安く、1万円以内で買えるものを3つ紹介」という記事で、選び方のポイントについて詳しく解説していますが、20~30Lあって普段使いできるものがおすすめ。
あとは、財布やスマホ、地図などの小物を入れるポケットが多いほど便利ですが、値段と相談です。
ザックの費用
ザックの費用は、
- 日帰り用:10,000円
- 一泊用:15,000円~20,000円
が目安です。
【登山用ザック】アルペン公式通販に移動する![]()
必要な装備その3:レインウェア
レインウェアは登山中に雨が降ったときに、持っていないと全身が濡れて、体温が奪われていきます。
命にかかわるので、必ず常備してください。
また、防寒着の代わりにもなります。

レインウェアの選び方
登山専用のもので、雨がしのげるものを選びましょう(安物の雨がっぱは、最低限の防水しかできないので意味がありません。)
「登山用のレインウェアを安く、1万円以内で買える商品を3つ紹介」という記事で、初めて登山する人向けのレインウェアを紹介していますが、ぶっちゃけ耐水圧は10,000mmもあればよいかと。
ただ、レインウェアは、雨に濡れるたびに劣化するというので。
年に数回、3,000M前後の山に頻繁に登るのであれば、「ゴアテックス製」(雨にぬれても劣化しない)のしっかりしたものを買うようにしてくださいね。
レインウェアの費用
レインウェアの費用は、本格的なものであれば、10,000円~20,000円が目安です。ゴアテックス製であれば30,000円以上。
「登山用のレインウェアを安く、1万円以内で買える商品を3つ紹介」という記事で、1万円以内で買えるレインウェアを紹介していますが、最もおすすめなのがティゴラのレインウェアの上下![]() です。
です。
5,500円以上(税込)買えば送料が無料なので、ヘッドライト等の他の登山用品と同時に買った方がお得です!
必要な装備その4:防寒着
防寒着は、頂上に到着したときに寒いことが多いので必要です。
最悪、低体温症になるので、常備しましょう。
防寒着の選び方
登る山の標高に合わせてください。
ただ、高い山に登らないのであれば「登山の防寒着は必須!だけど、低山ならレインウェアで代用も可能」でも書いていますが、レインウェアで代用は可能かと。
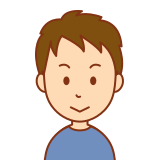
普通のダウンジャケットじゃダメ?

市販のダウンジャケットでも、ザックに入るのであれば代用可能です。
※そのかわり、土や砂で汚れてしまうのと、雨が降った時に傷んでしまう点は、要注意です。
防寒着の費用
防寒着をもし買うなら、
- 3,000M未満の標高の山の場合:10,000円~12,000円
- 3,000M以上の標高の山の場合:12,000円~16,000円
- ゴアテックス製の場合:30,000円以上
が目安です。
必要な装備その5:ヘッドライト
登山中に日が暮れて、暗くなった時、明かりは一切ないのでヘッドライトが必要となります。

一泊するのであれば、なお必須!
かといって、懐中電灯を持ちながら歩くのは危険なので、頭につけられるヘッドランプは必要です。

「登山用のヘッドライトは必須!予備電池も含めて必ず持っていく」という記事で詳しく解説していますが、ペルツのヘッドランプ![]() が有名どころ。必ず持って行ってください。
が有名どころ。必ず持って行ってください。
必要な装備その6:アンダーウェア
アンダーウェア(肌着)は、汗を吸い取る役割があります。
速乾性があること
普段、スポーツする際に使うもので代用可能なのですが(ヒートテックはNGです)。
登山中は汗の量が多いので、速乾性があることが条件となります(無視してたけどね。大学生の時は・・・)。
登山用のアンダーウェアを買う場合の費用
登山用のアンダーウェアは、3,000円~5,000円程度です。
【アンダーウェアを見る】アルペンの公式通販に移動![]()
必要な装備その7:登山用靴下
登山用靴下は、あるのとないのとでは、快適さがまるで変わります。
具体的には、
- 汗をかくので、足元がジメジメする
- 登山靴と普通の靴下はフィットしない
という点から登山用の靴下を買うことをオススメします。
登山用靴下と費用
夏山トレッキング用の登山用靴下の費用は1,000円~2,000円です。
【トレッキングソックスを探す】アルペンの公式通販に移動![]()
必要な装備その8:地図
地図は、これから登る山の「山と高原地図」(昭文社)を買います。
「山と高原地図」には、地図のほかに、
- 水場
- 小屋の情報
- 歩行時間(コースタイム)
- テント泊が可能な場所
といった山の基本情報を全て網羅している優れものです。
登山用品店でも買えますし、本屋さんやAmazonでも買えます。
山と高原地図の定価は、1,100円(税込)でありそれほど高くありません。
行く山域の「山と高原地図」は必ず購入してください。
【補足】できることなら地形図も持っていく
なお、正確な位置を把握するという観点から、できることなら地形図も、持参したいところです。

読図をするという点では、「山と高原地図」はいろいろと書き込んであるので不便です。
YAMAPというアプリで、5枚までという上限がありますが無料入手できます。
夏山登山で1泊以上するのに必要な装備
夏山登山で1泊以上するのに必要な装備を紹介します。

日帰り登山しかしない人は不要です。ここは、読み飛ばしても大丈夫!
夏山登山で1泊以上するのに必要な装備その1:登山用マット
登山用マットは、サーマレストかつ最安値を選んでおけば、冬の時期の登山でない限りは問題ありません。

よほどの山でない限り、登山用マットであれば、性能面はさほど気にしなくて大丈夫です!
登山用マットについての記事>>登山のマットは何がおすすめ?サーマレストかつ、最安値!
夏山登山で1泊以上するのに必要な装備その2:寝袋(シュラフ)
車中泊用の寝袋を買うと、結構しんどい思いをします。
必ず、コンパクトかつ、-10℃程度は耐えることができるものを選んでください。
夏山登山に必要な装備と費用についてまとめ
夏山登山に必要な装備と、費用は次の通りです。
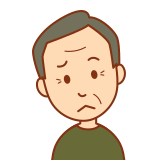
8つの中で、優先度はないの?
どれも、「必ず、いつかはそろえる」という条件であれば、優先順位は次の通り。
登山靴=ザック=レインウェア=防寒着>ヘッドライト=地図>>>アンダーウェア=登山用靴下
装備を揃えたら、次に初めて登る山を決めましょう。


コメント